七力研究所の近況 〜
|
||
|---|---|---|
秋月 涼 |
||
|
|
||
|
(一)
円筒形の密閉された透明なガラス瓶は、成人男性の手のひらを広げたくらいの大きさである。その中には、絵の具を溶かしたように鮮やかな青い水が半分ほど充たされており、瓶の上方にはタバコの煙に似た水色の気体が絶えずうごめいている。 以前、爆発事故を起こした影響で地肌が露わになっている丘の上で、二十四歳の冴えない青年は実験の準備をしていた。 彼はデリシ町出身のザーン族、名をテッテという。カーダ氏の運営する〈七力研究所〉の記念すべき四千人目の研究員であり、目下、ここの最長勤務記録を更新中の奇特な青年である。 町の雑貨屋で購入した簡素な木のスコップで二つの穴を掘り、森で拾った真新しくて頑丈そうな太い木の枝をそれぞれ埋める。左右に動かしてみて簡単には倒れないことを確認する。 それから二つの枝に錐(キリ)で穴を開けようとするが、やりにくくて仕方がない。そりゃそうだ――埋まっている木の枝に横から錐で穴を開けるなんて、歴戦の職人にとってさえ難しかろう。 『いつまでかかっとるんじゃ。日が暮れてしまうぞい!』 時折、苛立ちを隠しきれない雇い主のカーダ博士から風の魔法通信が届く。耳元で響く怒鳴り声に、彼は思わず手のひらに錐を刺してしまい、相手の罵りの音量に負けぬ悲鳴をあげた。 「ぎゃあぁ! いちちちち……」 情けない様子が、もともと短気なカーダ氏のさらなる怒りを買ったのは想像に難くない。それでも落ち込まないのがテッテの良いところで、彼はあくまでもマイペースに作業を再開する。 『なぜ、わしの弟子は、こうも出来が悪いのじゃろう……』 呆れて、ぶつぶつ呟いている師匠の小言も、馴れたものだ。 テッテは手順の悪さを反省し、結局は枝を掘り返して横向きに置き、不器用な手つきで錐を動かした。狙った場所が悪く、思うように進まない。それでも無理矢理のごり押しで二本の枝の上部に穴を貫通させ、茶色の大地へ丁寧に埋め戻した。 次は、あらかじめ持ってきて置いた綱を枝先の穴に通そうと思ったのだが、肝心の綱が見当たらない。地面を触って泥だらけになりながら、ようやく探し当てた頃には、大丈夫だと思っていた枝が一本倒れていたので、立て直し、下の方を塗り固めた。 穴に綱を通すのは楽だったが、冒頭のガラス瓶を固定するのが、また難儀であった。綱に強力な釣り糸を結びつけ、それを垂らして瓶のふたの小さな取っ手に引っかけるのだ。肩が凝って目が痛くなるほど失敗したあげくに、ようやく成功する。仕上げに乾いた小枝を積み重ね、焚き火が出来るように配置する。 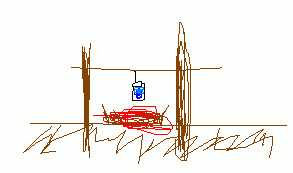
これでカーダ氏の描いた雑な設計図通りに一応の実験設備が完成した。青年は天空魔術の呪文を唱え、通信を飛ばす。 「師匠、こちらテッテです。準備が出来ました」 (二)
だが、テッテの呼びかけ虚しく、相手から聞こえてきたのは、遠い山から響いてくる獣の咆吼のような低いイビキと、歯ぎしりであった。どうやらカーダ博士は待ちくたびれて眠ったらしい。 「師匠、師匠、起きて下さい」 弱り顔で魔法通信を飛ばし続けるが、押しが弱いためか老人の反応はいまいちである。ただでさえ馴れない作業で疲れているのに、これ以上、余計な精神力を浪費するのはさすがに辛いと感じ、テッテは怒鳴られるのを覚悟で捨て身の賭けに出た。 「わあっ!」 出来る限りの大声を出し、一方的に通信を切断したのだ。 今度は心の準備が出来ている。テッテは少しずつ確実に夕方へ進んでゆく丘の上に腰を下ろし、相手からの反応をじっと待った。風通しが良いため吊されているガラス瓶が揺れ動き、時折、森のこずえは思い出したようにサラサラと唄っている。 かっきり三十回、心の中で数えた時、それは唐突に始まる。 『ふぁ……ゲホッ。いつまでかかっとるんじゃ、このたわけが! 夢幻の力の研究をしていたから良かったようなものの……』 カーダ氏は伝達魔術を通し、あくびをかみ殺した声で繰り返した。〈夢幻の研究〉とは要するに居眠りのことだが、経験上、テッテは敢えて深入りせず、相手をなだめつつ話を進めていく。 「済みません。それで、次のご指示は何でしょう?」 『そうじゃそうじゃ、大事な実験前だったわい……』 ようやく目的を思い出した老博士だったが、そのまま自分の世界に没頭してしまう。これは自信家のカーダ氏の悪い癖だ。誇らしげに語り出し、その饒舌の勢いは留まることを知らぬ。 『今までのわしの研究はどれも負けず劣らぬ一級品だったが、今回は特にすごいわい。昔のものを遙かに凌いでおる。何と言っても、自然の循環を再現する訳じゃからな。これが成功すれば、色々な分野に応用できるじゃろう。いわば重要な転換点となる基礎研究じゃ。高価な薬品を集めた甲斐があったわい』 「ふむふむ……なるほど」 テッテは別に嫌な顔ひとつせず、師匠の独白に相づちを打っている。研究内容に全幅の信頼は置いていないにせよ、その一方で雇い主の熱意を尊敬していたのも事実なのである。 それに、今度は向こうから届いた魔法通信なので応えるのは楽であった。カーダ氏の方が逆に疲労感を覚える結果となる。 『ウオッホン。とにかく火をつけるんじゃ。いきなり猛烈に燃やすんでないぞ。弱火で、じっくりと瓶の中を沸騰させる。その沸騰した様子を観察し、逐一、洩らさずに報告するんじゃ。良いな』 「わ、わかりました。精一杯、やらせて頂きます!」 テッテが応える直前、カーダ老からの通信は切られてしまう。発せられた声は行き場を失くし、自分の耳に虚しく届いた。 「ふぅ」 緊張感が緩み、小さな溜め息をつく。肩の力を抜き、左右に首を動かす。それから彼は両腕を上げて、大きく伸びをした。 (三)
「火炎の力で水が蒸発し、天空の成分と混じり合って雲が生成される。その雲から雨が生まれ、再び海に注ぐ。その繰り返しじゃ。完璧な理論。わしは……わしは、なんと賢いのじゃろう!」 山の中腹にある古びた小さな研究室で、樫(かし)の木の椅子に腰掛け、研究生活四十年・現在五十四歳、白髪混じりのカーダ博士は思いきりふんぞり返った。その眼鏡がずれてゆく。 「あわわわ」 後ろへ重心をかけすぎて椅子ごと倒れ、大音響を立てる。 「いつも理論は完璧のはずなんですがねぇ……」 その頃、テッテはぶつくさ言いながら火口箱と火打ち金を用意していた。さすがにいつもやっていることなので、慣れた手つきで火打ち金をこすり合わせ、刹那のきらめきを掬い取った。 「よいせ、っと」 そうして生まれたばかりの火の粉を保護し、燃え易い藁くずに移して大切に育てる。確固たる存在にしてから、いよいよ実験器具の足元に積み重ねてある枝に近づけ、内側で解放する。 弱い風にあおられ、上手い具合に枝はパチパチ音を立て始め、煙で瞳がしみる。テッテはカーダ博士に報告するため、やむを得ず魔法通信を使うことにした。精神力には限度があるため、電話のような〈相互伝達魔法・クィザロアム〉を使うのは控え、一方的に自分の声を飛ばす〈伝言魔法〉を使うことにする。 「ψ∫ιщяoaζ……音の精霊よ。 私の声をあの人のもとに届け給え。クィザーフ!」 カーダ氏は後頭部を撫でながら起きあがった。眼鏡を拾って憮然とした顔で椅子を立て直していると弟子から報告が来る。 『あ、ええと、無事に火がつきました。弱火を維持しています』 「よし。そのまま続けるんじゃ」 カーダ氏も同じ魔法で応答する。 根っからの研究人であるカーダ氏は、実験や研究に打ち込むと、くだらぬ怒りは一時的に頭の中から消えてしまうのだった。 そして弟子からの二度目の実験報告は氏を喜ばせた。 『瓶は暖まり、かなり曇ってきました。特に瓶の上の方、つまり天空の素が散りばめてある付近が最も濃度が高いようです』 椅子の上であぐらをかき、腕組みし、老博士はうなずく。 「よし、よし。予想通り雲が出来るんじゃな。じきに雨が……」 今か今かと次なる報告を待ちわび、カーダ氏はしきりに貧乏揺すりを繰り返す。いつも実験の度に落ち着きなく足先を動かすので、博士の特等席付近の床板だけが大きく沈んでいる。 「遅いわい、遅いわい、何をしておるんじゃ奴は!」 博士が堪忍袋の緒を切り、怒鳴り声を送信しようとした直前。良いタイミングで、若い弟子の弱々しい声が耳元で響いた。 『あの……遅れましてすみません。ええとですね、困ったことが起きました。瓶全体が曇り、水滴が付着したところまで順調だったのですが、瓶の下の方が、なぜか赤くなってきました』 「何じゃと!」 カーダ氏の頭の中で、瞬時に七力の計算が行われる。 彼の予定では、焚火によって氷水の力が負けて蒸発し、天空の力と化合して雲となり、さらには雨となって、再び注ぐはずだった。上手く調整すれば蒸発量と降雨量が同じになり、自然界では普通に行われている水の循環が実現するはずだった。 ただ、弟子の言葉を信じるならば、瓶の中に火炎の力が誕生したことになる。氷水と天空だけで循環する予定だった瓶の中の世界に、情熱の赤い火炎の力が紛れ込んでしまったのだ。 火があまりにも強ければ、対立する氷水のエネルギーは消滅する。ついには供給の止まぬ火炎の力が天をも焦がすだろう。 テッテの方はというと、少し危険を感じつつも、ぐつぐつと煮えたぎるガラス瓶を一心に観察していた。焚火は盛んに燃え、ガラス瓶は今やトマトジュースのように赤く染まりつつある。 その時、にわか作りの実験装置の柱となっている太い木の枝の一本が傾いたので、土の中に深く突き刺して直そうとする。 「あっ」 テッテの表情が凍りついた。 枝は倒れ、例のガラス瓶が火の中に落ちたのだ。 たちまち瓶は恋する少女のごとく真っ赤に染まった。 「こ、これは……」 今までの失敗の経験から、物事の危険なタイミングは嫌と言うほど分かるようになったテッテは、考える以前に身体が反射的に動いていた。防護のため頭を抱え、その場所を大急ぎで逃げ出したのである。それでも伝達魔法の呪文を唱え、師匠への報告の義務は何とか果たしたのは、ある意味で立派だった。 『ぎゃああ!』 「どうした!」 爆発音とともに、弟子からの魔法通信は途切れる。 「馬鹿もん、最後まで様子を見るんじゃ……」 精一杯の強がりはフェードアウトし、消えていった。 その日の夕暮れ。七力研究所から最も近い都市であるデリシ町は、全てが溶けるような深い秋の夕暮れを迎えつつあった。 雲をも染めあげ、いつもよりも赤みが強く、恐ろしいほど美しい空を見上げて、学舎に通うリュアは素朴な感想をつぶやいた。 「空が燃えてるね」 「すっごいなぁ」 その隣で、同級生で親友のジーナも目を丸くしていた。 二人は太陽が沈んでしまうまで、砂浜に立ちつくしていた。 | ||
(了) | ||
|
|
||
【この作品は"秋月 涼"の著作物です。無断転載・複製を禁じます】 |