


2007年 4月の幻想断片です。
曜日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
天 |
土 |
夢 |
気分 |
|
× |
△ |
− |
○ |
◎ |
☆ |
4月30日− |
|---|
「おじいさん、どこ見てるの?」
「……ずっとずっと遠くさ」
「まぶしくないの?」
「……まぶしいさ」

|
4月29日− |
|---|
地上では樹が
空では雲が
気持ちよさそうに手を伸ばす
新緑の季節(とき)
|
4月28日− |
|---|
激しい雨のあとで
雲の口がわずかに開いて
怖いくらいの夕焼けを垣間見た
|
4月23日− |
|---|
[食べ切れなかったもの(1)]
「ふぁ〜あ……」
口元を抑え、リュナンが生あくびをした。今日は学院の試験がある。勉強のため、ゆうべはいつもより夜更かししたのだった。
「食べ切れなかったんだね、ねむ」
隣で並んで歩いている同級生のサホの腫れぼったい目も、あまり開いていない。部屋の中にいるよりも外に遊びに出かけたくなるような朝の澄んだ青空の下、小鳥たちはいつも以上に楽しげに囁いているようだった。柔らかな春の風は花の香りを運んでくる。ズィートオーブ市の旧市街、通り沿いに整然と並ぶ三階建ての家々の窓には、赤や橙の花の鉢植えが並んでいる。
「えっ?」
少し遅れて《ねむ》ことリュナンが尋ねた。
すると、サホはゆったりとした口調で言う。
「溜まった眠気を、食べ切れなかったんじゃない?」
「うーん」
歩きながら、しばらく考えていたリュナンは、やがてうなずく。
「うん、そうかもね」
|
4月22日− |
|---|
電車は二本のレールを走り
車は二本の轍をつくる
飛行機は雲のレールを後に残し
人間は二本の足で歩き続ける
|
4月18日− |
|---|
[森の音楽会(1)]
好きな歌を口ずさみながら、森でいちばん大きな木の幹に背中を預ける。これ、最高っ!
下枝は刈ってあるから寄り掛かりやすい。枕代わりの幹や、椅子代わりの根はごつごつしてるけど、木の匂いがすごく近くて気持ちいい。きらきら光る木漏れ日とか、あたしとほとんど同じのを見てるんだろうなと思う――木も。
気分が良くなると、あたしは木の幹に身体を預けたまま、空の方を向いて好きな歌を口ずさむ。心のままに、適当に。
晴れた日なら太陽の光の雫があふれて、霧雨ならば水の滴がこぼれて、どちらも讃えてくれているかのよう。
ある時、あたしは気付いた。
歌をやめても、どこかで知らない音楽が続いているような気がしたんだ。鳥の歌や獣の遠吠えとは違い、いくつもの音が正確に重なっている感じがする。木が水や養分を吸うのとも違うみたい。音の調べは時に明るく、時に沈み、弾けたり静まったり。
すごく近いような、でも決定的に遠いような気もする。くぐもった微かな音はその間も響いていた――確かに。
すっかり音の源を探すのに夢中になっていたあたしは、やがて木の幹に耳を当てた。その瞬間、推定は確信に変わった。
この不思議な音楽は、幹の内側から聞こえてくるみたい。
幹の中で、音楽を奏でている人たち。
あたしはその人たちに会いたくなった。
|
4月17日− |
|---|
幅の広い河は緩やかに蛇行していた。これまでは半時計回りに進み、河原は左岸にあったが、しばらく直線になっていた。
その左側に、かつての河――三日月湖が、時計回りに残っている。この時間が止まった水にも、雨は次々と降り注ぎ、水は新しく洗われる。
私はここに居座っている。時間の大河は残酷なほど新鮮に流れているけれど、この三日月湖では進み方がゆっくりだ。
昔の人間たちは、わしらを神と呼んでいたようだ。静かで居心地がいいから、もうしばらく、ここに居座ることにしようか――。
|
4月16日− |
|---|
[小さな池の伝説(1)]
森の奥に人知れず眠っている小さな池がある。普段は銀色に似て、木々の間から光が注ぐと金色に映えた。夕暮れは空よりも紅に染まり、夜は北の空の星たちのように青白く瞬いた。
不思議なほど透き通った水を湛えた池には、魚などの生き物は棲んでいなかった。
池は鏡のように、その上に広がる森の木々を映していた。春は若葉を、夏は青葉を、秋の終わりは紅葉を、冬は枯れ葉と青空を。まれに、木の枝に留まる小鳥を映した。
風が吹けば水面は揺れ、雨が降れば雫が弾ける。雪が降れば冷たく沈み、花びらが来れば優しく浮かべた。
そういう緩やかな変化はあったが、流れ出す水も注ぎ込む川もない森の池は、全般的にはごくひっそりとたたずんでいた。
ある年の、ある晴れた朝早くのことだ。池の水面がゆらりと揺れ動いた。自然にというよりも、どこか作為的な揺れ方だった。
しぶきをあげ、銀色の水はすぐに大きく膨らんだ。それは丸くなり、ついには人の頭の形になった――。
|
4月11日− |
|---|
男が二つほど掌に載せていたのは、角砂糖に形も大きさも良く似た小さな立方体だった。角砂糖と違うのは色で、ガラスのように透き通っていた。うっすらと水色に見える気もする。
あたしはその妙な立方体を見つめていたが、分からないので顔を上げ、相手の表情を確かめながら尋ねた。
「これ、何?」
彼は口元を緩めた。
「何だと思う?」
相手が少し手を伸ばしたので、私は掌を差し出した。彼は血管が蒼く見える色白の手を斜めにして、二つの透明な角砂糖を私の掌の上に転がした。
「おっ」
予想外の触感で、あたしは思わず声を出した。それはひんやりとしていて、想像したよりもずっと柔らかかった。
そのプヨプヨした立方体を、あたしはしばらく指先で弄んだ。
「ますます、わかんない」
すると彼は、軽い小さな声でこう言ったのだった。
「固形にした雨さ」
|
4月10日− |
|---|
さっきまで西の空に残っていた夕暮れは急激に片付けられていた。夜の帳がおりて、空気はひんやりとした涼しい風に冷やされている。海が近く、潮の香りが雑ざっている。
「あっ」
僕はそのまま立ち止まった。瞬で他の考えは消えていた。気持ちが、その景色に吸い込まれていた。
昼と夜の分水嶺を越えてだいぶ暗くなった空の下で、なだらかな曲線を描く海の波打ち際だけ、鮮やかで優しく、見る者を引き付ける黄昏の朱みがはっきりと残っていたのだ。
暗い中で砂浜と海の境目だけが赤く縁取りされて浮かび上がり、波が寄せるたびに黄金の光がきらめいている。浴びるべき夕日は沈んだのに、あの海岸線はまだ夕焼けのままなのだ。
「きれいだったから、ちょっと残しておいたよ」
突然のことだった。背中の方から、男の子供の声――子供にしてはやや低い声が聞こえた。
「えっ」
その時、心の金縛りが解けた私は、驚いて振り返った。
景色が回転し、斜め下に顔が見えた。
そこには私の胸ほどの背丈しかない、澄んだ目の少年が立っていた。少年の横顔は夕日に照らされて真っ赤だった。
少年はかすかに微笑んだ。私は何も言えなかった。
海の方から涼しい夜風が吹いてきて、そちらに目を送った。
波打ち際の鮮やかな夕焼けは、幻のように消えていた。
振り替えると、少年もいなくなっていた。昼の名残とともに溶けてしまったのように。
こうして再び、本格的な夜が来たのだった。
|
4月 9日− |
|---|
「ふむ」
立て付けの悪いドアを開け、しばらく直立したまま上の方を眺めていたカーダ博士は、やがて不愉快そうに閉めた。
「ふん」
「あの、何かあったんですか」
弟子のテッテが恐る恐る尋ねた。すると弟子よりもだいぶ背丈の低い師匠は、手を動かさず首と目を動かして外を示した。
「見てみい」
「これは……」
テッテは絶句した。半開きにしたドアの向こうで、巨大な銀色の蜘蛛が巣を作っている。人の顔と同じくらいの大きさがある。
思うところがあったのか、試しに小さな紙片を丸めて投げ込む。刹那、まばゆい光が輝き、あっという間に黒焦げになった。
開ける時とは打って変わって、テッテは慎重にドアを閉めた。困惑し、助けを求めるように師匠のカーダ博士の方を見た。
「参りましたね」
「分かっとる。ゆうべの雷じゃ。今ごろ成功しおって」
カーダ博士は悔しそうに唇を噛みしめた。
ゆっくり進む光の研究の一環で、彼らはゆっくりした稲妻を作ることに没頭し、その中で雷の糸を小さな蜘蛛に編ませる実験をした。昨日の段階では失敗かと思い、蜘蛛を表に放置した。
しかし、こうして今朝になると大きな蜘蛛が稲妻の巣を張って、研究所の入口をふさいでいたのだった。言うなれば玄関に一触即発の雷が居座っているような状態だった。
|
4月 8日− |
|---|
時と心に余裕があれば
いろんなものが見えてくる
道端の草花
人々の服装、笑顔
そして、こころ
|
4月 7日− |
|---|
澄んだ目をしているのは
きっと覚悟を決めているから
もはや
多くの言葉は必要ない
お疲れ様、そして
ありがとう
|
4月 6日− |
|---|
「あの時、わたし思ったの」
筆を止めて、顔をあげ、ミレイユは落ち着いた口調で言った。
「雨粒が窓ガラスに引いた線、風が湖面に引いた線、それから光が森の中に引いた木々の影……雨上がりの虹」
彼女は茶色の瞳をゆっくりと瞬きさせてから、続きを語った。
「ルデリア大陸自身が持っている、絵筆なんだってこと」
私がうなずくと、彼女は大空を仰いで、こう言った。
「海でも空でも、パレットにはたくさん水があるみたい」
|
4月 5日− |
|---|
「水?」
下に降りてゆく狭い階段の先――足元のあたりにランプの明かりを当てると、深い緑色の液体が鈍く輝いた。腐った水にしては澄んでいるし、臭いもしない。
「臭くないな、むしろ……」
気のせいか、心地よい木や草の香りが混じっているような。
「水か?」
相棒が後ろから覗き込むようにした。俺はさっき思わず止めた足を、ゆっくりと前に進めていく。
濃い緑の液体は、何の抵抗もしなかった。飛び散ることも跳ねることもなく、靴を吸い込んだ。
「何だこれ。空気か?」
俺は目を丸くし、またランプを近づける。どうやら階段の奥の方にぼんやりと明かりが燈っているようだ。ゆらゆら揺れていて朧(おぼろ)げだが、間違いない。
俺は息を吸い、落ち着いて吐き出してから言うのだった。
「行くぞ」
|
4月 4日− |
|---|
[黄緑の光]
まばゆい木漏れ日が、木々の枝と枝、葉と葉の間からあふれ出して降り注ぐ。まぶしそうに額に手を当てて、十四歳の村娘、シルキアが言った。
「黄緑の光……」
ルデリア大陸は南の方から、また海に近いところから春が染み込んできていた。山奥のサミス村はまだ寒暖の差が激しかったが、光はもうすっかり春の日差しだった。
「池とか、湖の中だと、青い光になるのかなあ」
木の幹に身体を預けていたシルキアの目の前を、まるで風に吹かれたリボンのように、黄色の蝶々がひらひらと飛んでゆく。
「あっ」
思わず手を伸ばしかけた時、掌につかんだのは――。
つくしを起こし、花を目覚めさせる一陣の春の風だった。
「シルキア〜、どこなのだ〜っ?」
三つ年上の姉のファルナの呼ぶ声が聞こえてきた。シルキアは身を起こし、右手を口に当てて、高らかに声を張り上げた。
「お姉ちゃ〜ん、あたしはここにいるよ!」
それから少女は微笑み、樹を仰いで小さく優しく語りかけた。
「この季節の始まりに、ね」
風が吹いて新緑は揺れ、波のように返事をするのだった。
|
4月 3日− |
|---|
はちみつを載せたクッキー食べながら、
画用紙に描いた空は〈水の色〉。
早く天気にならないかなあ。
|
4月 2日− |
|---|
洞窟の奥深くに白い風の群れがいて、
重々しくゆっくりと掻き回していた。
澄んだ青空から洞窟の穴を縫って降り注ぎ、
音も無く溜まってゆく細い光の湖を。
しだいに搾られた光は深い青の水になって、
下の階層に滴り落ちている。
なぜか薄明るい洞窟の底、
空色の鍾乳石が伸びる広い空間に。
はるばる私は、それを汲みに来たのだ。
さあ、小瓶の口を雫にかざそう。
ひとしずく――
青空のエキスが、瓶の中に吸い込まれていった。
|
4月 1日− |
|---|
淡い桜の花は
薄曇りの空に映える
あの花が桜吹雪になると
新緑の季節がはじまる――
そんな気がする
|
|
|---|
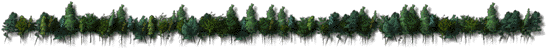
|



|
|