


2009年 1月の幻想断片です。
曜日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
天 |
土 |
夢 |
気分 |
|
× |
△ |
− |
○ |
◎ |
☆ |
1月31日− |
|---|
[雪の声]
「あっ」
扉を開けると、まばゆい光の洪水と冷たい風の洗礼で、リンローナは一瞬目を閉じた。少女はゆっくりとまぶたを開けてゆく。
「ゆうべ、また積もったんだね!」
声が弾む。道は銀の帆布(はんぷ)になっていた。町外れのこの辺りでは通りかかる人も少なく、足跡も馬車の轍も少ない。
「おう」
後ろから来たケレンスが生返事をする。こちらは寒そうに腕組みをし、軒先から伸びた氷柱から零れ落ちる水滴を目で追う。
「よいしょ」
しっとりと湿って凛と張りつめた冷たい空気の中で、玄関の小さな屋根の下に薄く積もっていた雪に足跡を残し、リンローナは長靴の右足を持ち上げて、そっと真っ白な地層へ踏み下ろす。
キュッ。
圧縮された新しい雪が、ネズミのように鳴いた。
「かわいいっ♪ あたし、この音、大好きなんだ〜」
キュッキュと踏みしめ、はしゃぎながら歩いていたリンローナは、玄関から見守っているケレンスの方に笑顔で振り向いた。
「滑って転ぶなよなぁ」
そう言ったケレンスの声と表情は柔らかで、穏やかだった。
温かな光が降り注ぎ、空は蒼く、いい一日になりそうだった。
|
1月30日− |
|---|
「雨粒の迷宮……」
リュアがうっとりとつぶやく。
霧の中に差し込む光は、漂う雨粒たちから抜け出せず無数に反射して、不思議な七色の世界を形作っていた。本来は白いはずの光も霧も、今は虹を砕いたかのように、赤、青、紫、黄色、緑、橙、水色がゆったりとシャボン玉のように入れ代わる。
「きれいだけど、変な霧!」
ジーナは面白そうに叫び、しきりに両手を動かして、移ろいゆく色の変化を楽しむのだった。
|
1月29日− |
|---|
あの晩、円く明るい月が見え隠れしていた
隠していたのは、雪だった
雪雲ではなく、あれは雪そのものだった
月の辺りにだけ、うっすらと雪のヴェールがかかっていた
そしてそこから切れ切れの光の糸が降り注いでいた
|
1月28日− |
|---|
「川はなだらかに下ってゆく
この流れをたどってゆけば
いつか海に着ける」
しっとりと、それでいて熱っぽく、セラーヌ町の酒場で女性が唄っていた。メラロール王国の内陸にある草原の町セラーヌでは、海沿いの町からやってきた交易の商人や兵士なども少なくない。彼らはしばし言葉を休め、郷愁の声に耳を傾けていた。
窓から洩れるランプの光が、しんしんと降り続いている外の雪に黄金の輝きを投げかけていた。
|
1月27日− |
|---|
朝日の最初の輝きを掬い取る――
それはとても尊いものなの
細やかな銀の粉が星のかけらのように舞い飛ぶ
まるで花びらのように
|
1月25日− |
|---|
「湯気が出てたから、てっきり温泉の川だと思ったのよ」
少し不愉快そうな口調で、シェリアが語り出した。
「で、思わず手を差し入れてみたら、氷みたいに冷たくて……」
「きっと風のほうが水よりも冷えていたんですね」
北国出身のタックが冷静に言い、同郷のケレンスが続いた。
「メラロール王国の寒い朝じゃ、当たり前のことだぜ」
「何よ。いやな国ねえ」
赤くなった手をさすりながら、大陸の南からやってきたシェリアが口を尖らせ、不満げに呟いた。
太陽は少しずつ天の坂を歩き始め、そろそろ葦の間を走る小川から立ちのぼっていた霧も収まってくる頃合いだろう――。
|
1月13日− |
|---|
[この冷たさを]
「この冷たさを結晶にしたら、どうなるのかな?」
シルキアが言った。窓は曇っているが、雪の照り返しは明るく、部屋の中に入り込んでくる。つららから水の滴る音が響く、山奥の村の穏やかなひとときだった。
「そうですねぇ」
温かなスープの入ったカップから立ちのぼる。湯気の不思議な広がり方と消え方を見つめながら、賢者のオーヴェルは考えていた。
「きっと、氷の固まりになるのだと思います」
「湖みたいな?」
すかさず、向かい合う席に座るシルキアが訊いた。このあたりの湖は、冬になると凍りついて、新しい道になるのだった。
「湖というよりも、山のようになるかな」
オーヴェルが答え、シルキアは興味深そうにうなずいた。
「ふーん」
「それほどに冬の冷気は大きいのだっ?」
シルキアの横に座っている姉のファルナが口を開いた。
「ええ。そうですね」
オーヴェルは即答し、それから表情を少し緩めて言った。
「でも、せっかく冷たさを抜き取って結晶にして、そんなに巨大な氷が生まれてしまっては、すぐに冷気が漂ってしまいそうですね。風は春のような温かさになるのだから、溶けてしまって」
「そっか! やっぱり駄目なんだね」
シルキアは少し残念そうにうなだれ、ファルナはうなずいた。
「寒さは、我慢するしかないですよん。でもファルナは、この冬の透き通った寒さが、それほど嫌いじゃないのだっ」
「もう少し冬が短くなるといいのだけれど」
その声は、厨房から現れた姉妹の母の声だった。ファルナ、シルキアと客人のオーヴェルは、顔を見合わせて微笑んだ。
|
1月 3日− |
|---|
あと少しで見えそうなくらい透明な闇を切り裂いて、鋭い風が駆け抜けてゆく。
ちらちら揺れる星たちは、凍える世界の果てで不思議なほどに明るく冴え渡っている。
あれは何の言語だろう――。
きっと、あれこそが夜空に見つけた光の歌。
四次元の楽譜なのだ。
|
1月 2日− |
|---|
誰かが、ぽつりと窓を叩いた。それは小さな呟きのようであり、僅かな軋みのようだったが、音の途絶えた冬闇の奥底では隠しきれないほどの存在感を持っていた。
夜更けのことだ。
(誰?)
あとはランプを吹き消して冷たい布団に潜るだけだったフィアーナは、はっとして顔をあげた。
その表情がランプの明かりの隅で少し和らぐ。
(誰もいるわけない。だってここ、二階じゃない)
少女は吐息の霧とともに、ランプを窓に近づける。
フィアーナは思わず息を止め大きくまばたきした。
薄い硝子の向こうに、流れ星の粉であるかのような、金に照らされた斜めの線が一瞬だけ輝いた。
「雨……」
向き合う窓の外は別の世界だった。降り始めた雨は、早くも本降りを迎えようとしていた。
(氷になりきれない――)
そのひとしずく、ひとしずくが、過ぎ行く一日ごとであるかのような。
(雪になりきれない、雨)
フィアーナは一心に目を見開いて、寒さも忘れたかのように、しだいに曇りゆく窓のかなた、天から降りてくる季節の贈り物を見つめていた。
|
|
|---|
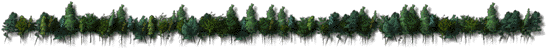
|



|
|